小惑星ヘラクレスは、近年注目を集めている占星術上の天体のひとつです。1991年に発見された実存する小惑星であり、その特徴や分類や公転周期、地球との接近軌道など、天文学的なデータにもとづいた理解が深まりつつあります。
名前の由来は、古代ギリシャ神話に登場する英雄ヘラクレスにあり、特に有名な「12の試練」のエピソードは、この天体の象徴的な読み解きに大きな影響を与えています。
占星術においても小惑星ヘラクレスは、困難を乗り越えて成長する力や、試練との向き合い方を示す象徴として重要な位置づけにあります。その特徴と意味を探ることで、個人の内面的な資質や人生のテーマをより深く理解する手がかりとなるでしょう。
現在のところ、ヘラクレスには公式な記号は設定されていませんが、一部の実践者の間では非公式なシンボルが使われることもあります。
また、四大小惑星との比較を通じてその独自性を把握することで、より立体的な解釈が可能になります。
この記事では、小惑星ヘラクレスに関する基本情報から、アスペクトの事例、ハウスの事例、さらにはマイクタイソンの鑑定事例までを通して、占星術的な視点からその可能性を幅広く解説していきます。
チャート上でこの天体が示すテーマに関心のある方は、ぜひ最後までご覧ください。
- 小惑星ヘラクレスの天文学的特徴と分類について理解できる
- 神話や12の試練に基づく象徴的な意味を知ることができる
- 占星術におけるアスペクトやハウスでの解釈方法が分かる
- 実際の鑑定事例や著名人との関連性を把握できる
小惑星ヘラクレスとは:占星術の基本情報

- 実存する小惑星ヘラクレスの特徴とは
- 小惑星番号から見る分類や公転周期
- 小惑星ヘラクレスの記号は存在するのか
- ヘラクレス神話と12の試練について
- 小惑星ヘラクレスのネーミング由来を探る
- 四大小惑星との違いや関係性
実存する小惑星ヘラクレスの特徴とは
小惑星ヘラクレス(Heracles)は、1991 年11 月7 日にパロマー天文台でキャロライン・S・シューメーカーが発見された実在の天体であり、正式には「5143 Heracles」として知られています。
この小惑星は、地球近傍小惑星(NEA:Near-Earth Asteroid)に分類されるアポロ群に属し、その軌道は地球の公転軌道と交差するタイプです。
これは、ヘラクレスが他の主帯小惑星とは異なり、地球に接近する軌道を持っていることを意味します。
また、ヘラクレスは「二重小惑星(二重天体)」と呼ばれるタイプでもあります。
これは、主天体の周囲に小さな伴星が存在している状態であり、重力的に結びついた二つの天体が一対で運動している構造です。
地球からの観測ではその伴星の存在は明確に確認されており、小惑星全体としての物理的な構造にも注目が集まっています。
サイズは直径約4〜5キロメートルと比較的小型であり、表面は主に岩石質と考えられています。
このような特徴を持つことから、小惑星ヘラクレスは科学的にも占星術的にも興味深い存在です。
特に占星術においては、彼の神話的背景や物理的特性が、人間の「試練への挑戦」や「力の象徴」としての意味合いに直結すると解釈されることが増えています。
天体としての実在性と軌道特性が示す「地球との接近」もまた、象徴的な読み解きにつながる要素といえるでしょう。
小惑星番号から見る分類や公転周期
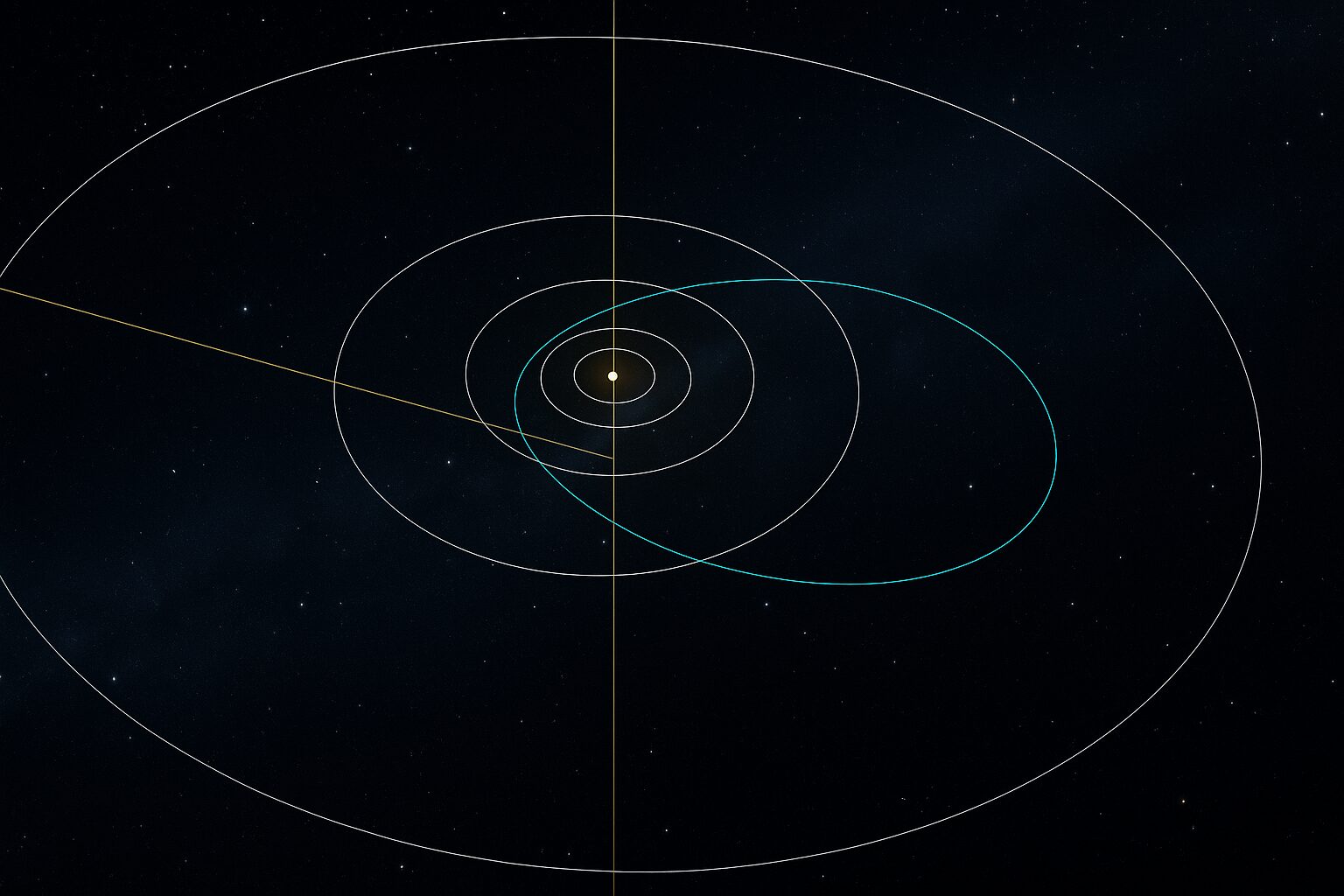
イメージ画像
小惑星ヘラクレスには「5143」という小惑星番号が割り振られています。この番号は、発見の正式登録と承認を経た後に与えられるもので、占星術に取り入れる際の基本的な識別情報としても重視されます。
番号が若いほど古くに発見されたことを示しており、5143番というのは比較的新しい分類に属する小惑星だといえます。
小惑星の分類方法にはいくつかありますが、最も基本的なのが軌道に基づく分類です。
ヘラクレスの場合、アポロ群に分類されており、これは公転軌道が地球の軌道よりも外側で、かつ交差するタイプを指します。
アポロ群に属する小惑星は、しばしば地球に接近するため、科学者たちの間では地球衝突リスクを監視する対象にもなっています。
また、ヘラクレスの公転周期は約 2.48 年 (907 日)とされています。これは、太陽の周りを一周するのに地球の2.5倍の時間を要するという意味です。
地球と周期的に接近する軌道を持つことから、観測タイミングによっては明るく見えることもあります。
占星術の視点では、この公転周期の短さが重要なポイントです。比較的短期間で星座間を移動するため、個人チャートの中でより頻繁にアスペクトやハウス配置が変化する可能性があり、動的な象徴として作用することが期待されます。
短い周期ながらもインパクトのある象徴性を持つ天体として、小惑星ヘラクレスは占星術的な解釈に多様性をもたらす存在といえるでしょう。
小惑星ヘラクレスの記号は存在するのか
小惑星ヘラクレスには、現在のところ正式に承認された「記号(グリフ)」は存在していません。
これは、小惑星全体の中でも一般的な状況です。もともと惑星や主要な天体には、天文学や占星術の歴史の中で自然発生的に記号が生まれ、広く使われてきました。
しかし、小惑星の発見数が急増した20世紀以降、その全てに固有の記号を付けることは実用的ではなくなったため、多くの小惑星は番号と名称で識別されるようになったのです。
例外として、セレスやパラス、ジュノー、ベスタといった四大小惑星には、それぞれ固有の記号が存在します。これらの天体は早期に発見され、天文学上も占星術上も重要視されていたため、記号が付与され、今でも使用されています。
一方で、小惑星ヘラクレスのように比較的新しく発見された天体については、公式な記号はまだ設定されていません。
ただし、一部の占星術家や実践者の間では、非公式ながら独自のシンボルやアイコンが使われ始めている事例もあります。これは、チャート作成時の視認性や記憶しやすさを高めるための工夫として、個人や団体レベルで試行錯誤がなされている結果といえます。

Astro Goloの例
したがって、占星術における実用性を高めるためには、将来的にヘラクレス専用の記号が広く採用される可能性も十分に考えられます。
占星術が実践者の創意工夫によって発展してきた歴史を踏まえると、このような柔軟なアプローチはむしろ自然な流れといえるでしょう。
記号の有無に関わらず、天体が持つ意味や象徴性を丁寧に読み解く姿勢が何より大切です。
ヘラクレス神話と12の試練について

古代ギリシャ神話におけるヘラクレスは、神と人間の間に生まれた英雄であり、その力強さと不屈の精神で知られています。
ゼウスと人間の女性アルクメネの子として誕生したヘラクレスは、天界と人間界の両方に関わる特別な存在でした。
しかし、その出生が原因でゼウスの正妻であるヘラの怒りを買い、幾度も試練や災難に見舞われることになります。
その中でも特に有名なのが、「12の試練(ヘラクレスの12功)」と呼ばれる壮絶な課題です。
これは、ヘラの策略によって一時的に錯乱し、自らの家族を手にかけてしまったヘラクレスが贖罪のために課されたものです。
試練の内容は極めて困難で、たとえば「ネメアの獅子を素手で退治する」「ヒュドラーと呼ばれる多頭の蛇を討伐する」「アウゲイアスの家畜小屋を一日で清掃する」といった、常人では不可能とも思える難題ばかりでした。
これらの試練は単なる肉体的な強さを問うものではなく、知恵、機転、精神力も求められるものでした。
各試練に対するヘラクレスの取り組み方は、時に仲間の協力を得ながらも、基本的には自らの力で乗り越えるという姿勢に貫かれています。
そのため、古代から現代に至るまで、ヘラクレスは「困難に立ち向かう意志と自己超越の象徴」として語り継がれてきました。
占星術においても、この12の試練は重要な象徴として用いられます。ちょうど12星座や12ハウスと一致するところも興味深いですね。
たとえば、チャート上の小惑星ヘラクレスが個人のどのハウスにあるか、またどの天体とアスペクトを形成しているかを通じて、「その人が人生でどのような困難を乗り越えるのか」「どのような形で自己成長するのか」といったテーマを探るヒントになることがあります。
このように、神話と占星術は深く結びついており、特にヘラクレスの神話的背景は、個人の強さや精神的成熟に関する象徴として極めて豊かな読み解きを可能にします。
ネーミング由来を探る
小惑星に名前が与えられる際、単なる記号的なラベルではなく、しばしば文化的・神話的な背景が強く反映されます。
小惑星ヘラクレス(Heracles)も例外ではなく、その名は古代ギリシャの英雄ヘラクレスに由来しています。英語圏では「ヘラクレス(Hercules)」と表記されることもありますが、天文学上の正式な命名ではギリシャ語形の「Heracles」が採用されています。
小惑星名は、国際天文学連合(IAU)の命名委員会によって承認されたのち、正式に登録されます。
多くの場合、発見者が命名の提案を行い、それが承認されれば名称として採用されます。ヘラクレスという名が選ばれた背景には、この小惑星の軌道特性や天文学的な個性と、神話上のヘラクレスの特性がある程度一致していると解釈された可能性があります。
たとえば、小惑星ヘラクレスは地球軌道に接近するアポロ型天体に属し、また連星(伴星)を持つことが確認されている点でも、他の小惑星とは一線を画す特徴を持っています。
この「他と違う、並外れた存在」という印象が、神話に登場するヘラクレスの「超人的な存在感」と重ね合わされたと考えると、命名の意図がより明確に浮かび上がります。
占星術の立場から見ると、天体の命名はその象徴的意味を解釈する際の出発点になります。
つまり、「なぜその名前が与えられたのか」「何を象徴しようとしているのか」という問いに対する理解が深まることで、チャートの読み取りにも説得力が増すのです。
小惑星ヘラクレスの名が持つ神話的背景は、単なる美称ではなく、占星術的な象徴性を裏付ける根拠として注目される要素だといえるでしょう。
四大小惑星との違いや関係性

小惑星ヘラクレスは、占星術で伝統的に重視される「四大小惑星(セレス、パラス、ジュノー、ベスタ)」とは異なる立場にある天体です。
これら四大小惑星は、19世紀初頭に発見された比較的古参の小惑星であり、いずれも女性神にちなんだ名前が付けられています。
それぞれ「母性」「知性」「パートナーシップ」「献身」など、人間の内面的な側面を象徴するとされ、チャート上では補助的な役割を担いながらも非常に深い解釈が可能です。

一方で、小惑星ヘラクレスは男性的なエネルギーを象徴する天体として注目されています。
神話の中でもヘラクレスは極めて行動的かつ個人主義的な側面を持ち、試練を乗り越える力、自己鍛錬、達成意識といったテーマと結びつけられます。
つまり、四大小惑星が「内なる働き」や「関係性」に焦点を当てているのに対して、ヘラクレスは「外向きの意志」や「社会的な達成」といったテーマを強調する傾向があります。
また、天文学的にも違いがあります。四大小惑星は主に火星と木星の間にある「メインベルト(小惑星帯)」に属していますが、ヘラクレスは地球に近い軌道を持つアポロ型小惑星であり、分類上も異なる領域に位置しています。
このため、四大小惑星に比べて軌道が不安定で、より動きがダイナミックである点が特徴です。
占星術の活用においては、四大小惑星との比較により、ヘラクレスの持つ役割が明確になります。
内面的なバランスと外的な試練の対比、女性的なエネルギーと男性的な力動の象徴など、多角的に解釈を深める手がかりとなります。
こうした視点は、個人の成長プロセスや人生のテーマを多面的に読み解くうえで非常に有効です。鑑定にはぜひ取り入れたい要素とも考えています。
小惑星ヘラクレス活用:占星術の読み解き方

- 占星術におけるヘラクレスの象徴
- 占星術におけるヘラクレスの特徴と意味
- ヘラクレスのアスペクトの事例解説
- ヘラクレスのハウスの事例分析
- 小惑星ヘラクレスとマイクタイソンの関係
- どう読むか?解釈の実際
占星術における「ヘラクレス」の象徴
占星術において、小惑星ヘラクレスは「試練を通じて鍛えられる力」や「人間としての成長の可能性」を象徴するとされています。
神話上のヘラクレスが12の困難な試練を通じて英雄へと成長したように、この小惑星も、苦難や障害を乗り越えることによって自らの力を証明し、内面的な成熟を獲得する姿勢を象徴しています。
この象徴性は、単に肉体的な強さや行動力にとどまりません。むしろ、自分に与えられた課題を受け入れ、それにどう取り組むかという「精神的なスタンス」や「人生哲学」の在り方に焦点が置かれています。
自分自身との闘いを含むすべての試練が、自己超越の契機になる――このような視点から、ヘラクレスは個人の成長テーマやチャレンジの方向性を示唆する重要な天体と考えられます。
また、英雄ヘラクレスが「神に近い人間」として描かれることもあり、占星術においては「人間の限界を超える能力」や「潜在能力の開花」といった意味でも解釈されることがあります。
これを現代的な視点で見れば、強いプレッシャーの中でこそ能力が発揮されるタイプ、あるいは社会的な役割を担うリーダーシップ的資質を象徴するとも言えるでしょう。
そのため、個人のネイタルチャートにおけるヘラクレスの位置は、ただの装飾的要素ではなく、重要な象徴的ヒントを与えてくれる可能性を秘めています。
占星術におけるヘラクレスの特徴と意味
占星術のチャートにおいて小惑星ヘラクレスを読み解く際、まず注目すべきはその「課題に対する向き合い方」を表す天体である点です。
この小惑星は、他の天体と異なり「どのような試練に直面し、それをどう克服するか」というプロセスそのものに焦点を当てる特徴があります。
例えば、ヘラクレスがアセンダント近くに配置されている場合、その人は人生の早い段階で強い挑戦を経験し、それを乗り越えることで他者から尊敬を集めやすいタイプと考えられます。
一方で、IC(イムム・コエリ)や月と絡む配置にある場合、家庭や感情面での試練を通して精神的な強さを築いていく傾向があるかもしれません。
ヘラクレスの意味は「勝利」「達成」「英雄的行動」などポジティブな側面が目立つ一方で、「過剰な自負心」や「試練を自ら引き寄せてしまう性質」などの注意点も含まれます。
自らの力を証明しようとするあまり、他者との軋轢を生んでしまうケースや、無意識に困難な状況へ突き進んでしまうことがあるため、過度な自己犠牲にならないような自己認識が求められます。
こうした観点から、小惑星ヘラクレスは一種の「成長促進剤」のような天体として理解することができます。苦しみや困難が避けられないものであるならば、それをどう受け止めて活用するか。その視点が、この小惑星の特徴を正しく活かす鍵になると言えるでしょう。
「ヘラクレス」のアスペクト鑑定事例解説
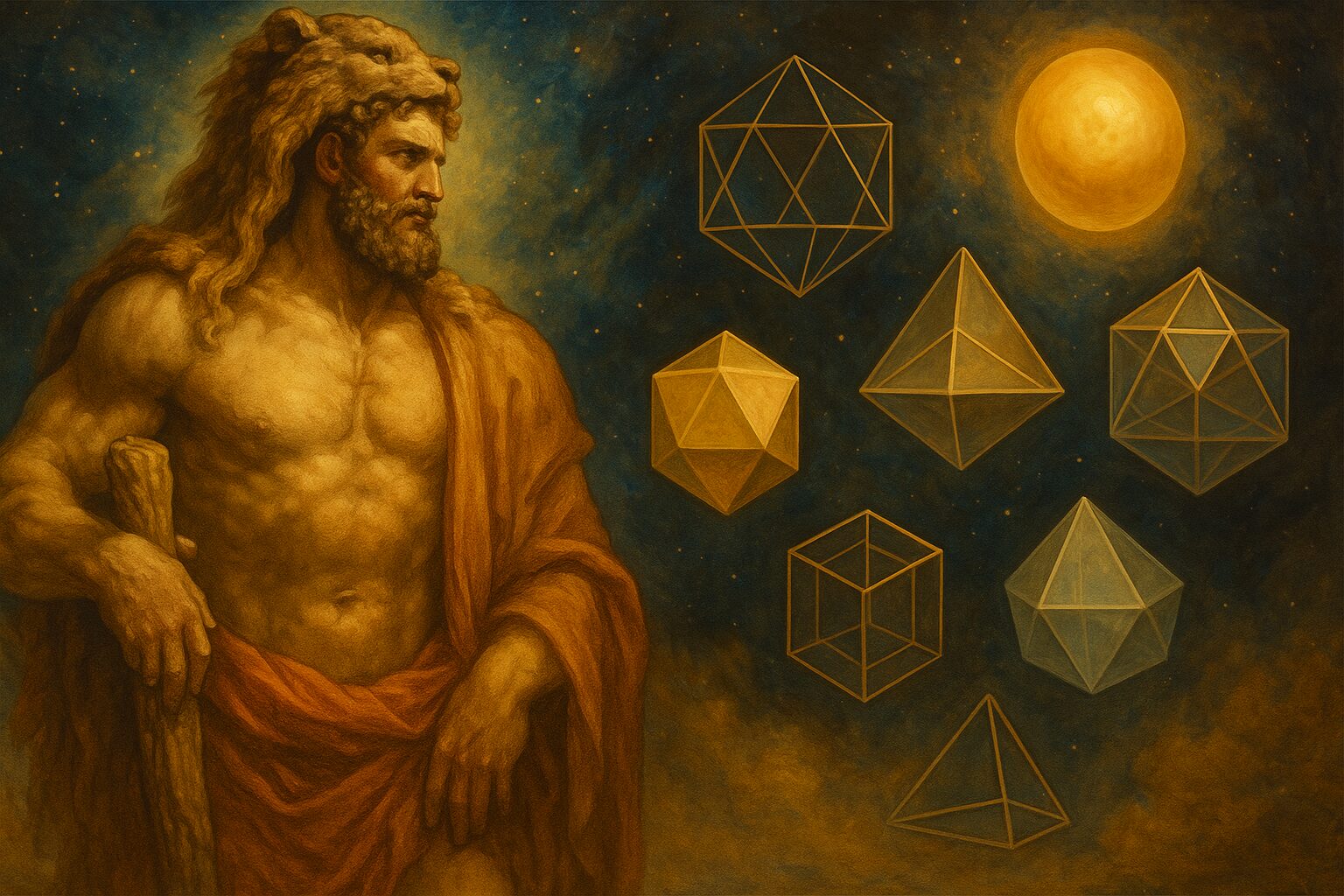
小惑星ヘラクレスが形成するアスペクト(天体間の角度関係)は、その人がどのような形で試練と向き合うか、またそれに伴って何を学び成長していくかを表す重要な手がかりとなります。
ここでは実際の事例をもとに、ヘラクレスのアスペクトが持つ意味を解説します。
例えば、ヘラクレスと太陽がコンジャンクション(0度)にある場合、その人は自分の生き方全体に「挑戦」や「課題解決」というテーマが色濃く影響します。
リーダーシップを発揮する場面が多いものの、しばしばプレッシャーの強い状況に置かれ、それを突破することが本人の自己確立につながる傾向があります。
また、ヘラクレスが土星とスクエア(90度)を形成しているケースでは、外部からの制約や義務によって試練を課されやすくなります。
このようなアスペクトは、ある種の「重圧に耐える力」を意味しており、努力と継続によって成果を生み出す堅実な成長を促します。課題は厳しいものの、その分得られる成就感も大きい構図です。
一方、ヘラクレスと火星がトライン(120度)を形成している場合には、行動力と試練の乗り越え方がスムーズに連携するため、危機的状況をチャンスに変える力を持つと解釈されます。
物理的な挑戦、たとえばスポーツや過酷な仕事環境で力を発揮することも少なくありません。
このように、アスペクトの種類や関係する天体によって、ヘラクレスの意味は多様に変化します。アスペクトの角度だけでなく、サイン(星座)やハウスの位置と合わせて読むことで、より深い人物像や人生の傾向を読み解くことが可能になります。
どのようなアスペクトであっても、その本質は「困難と成長の関係性」にある点は共通しています。試練は単なる障害ではなく、その人を磨き上げる装置として機能するのです。
ハウスの事例分析
小惑星ヘラクレスがどのハウスに位置しているかは、その人が人生のどの領域で試練を経験し、成長を遂げていくかを示す重要な指標となります。
占星術におけるハウスは人生の活動分野を意味しており、そこに配置される天体の性質によって、その人の生き方やテーマに深い示唆を与えます。
ヘラクレスは「試練と克服」「自己超越」「困難の中にある可能性」などを象徴するため、配置されるハウスごとに、その人がどのような形で力を試されるのかが明らかになります。
例えば、第1ハウスにヘラクレスがある場合、自己のアイデンティティそのものが課題の対象になります。
この配置では、他者からの期待や社会的な役割に押しつぶされそうになりながらも、自分らしさを模索し続けることになります。その過程で、人前での緊張や自己主張の苦手さを乗り越え、強い存在感を築く可能性が高いです。
第6ハウスにある場合は、仕事や日々の義務、健康管理といった日常生活の中で挑戦が生じやすい傾向があります。
ここでは、職場での責任やルーチンの中でのストレスをうまく対処する力を養う必要があり、地道な努力が試される分野と言えるでしょう。しばしば「働きすぎ」「自己犠牲的な働き方」になりやすい点も注意が必要です。
一方、第10ハウスに配置されている場合は、社会的評価やキャリアの分野で試練が現れやすくなります。努力がなかなか認められない、あるいは高い目標を課せられることで、自分の力を試される局面が多くなります。
しかし、それを乗り越えたとき、他者には真似できない独自のキャリアや役割を確立する力となるのです。
このように、ヘラクレスが入るハウスによって、その人がどの場面で「英雄的努力」を求められるかが変わります。
それは一時的な困難ではなく、生涯を通じて意識し続けるべきテーマであることも少なくありません。占星術におけるハウス分析は、天体の象徴を生活の具体的な領域に落とし込むための有効な手段といえるでしょう。
また、ヘラクレスがある対面のエリアも確認したいところです。対面の星たちの課題を乗り越えることで、大きな自己超越や、新たな可能性が見つかるという読み方もあると考えています。
小惑星ヘラクレス鑑定事例:マイク・タイソン

マイク・タイソンという人物は、見た目もさることながら、まさに「ヘラクレス的存在」と言っても過言ではありません。
彼のネイタルチャートを見たとき、小惑星ヘラクレスの位置が示す象徴と、彼の人生そのものが強く重なっていることに気づきます。ここでは、占星術的視点から見たタイソンとヘラクレスの象徴的関係を探ってみましょう。
タイソンは、若くしてボクシング界に彗星のごとく現れ、圧倒的なパワーとスピードで世界王者に上り詰めました。
その一方で、少年期からの過酷な環境、法的トラブル、社会的批判、精神的苦悩など、まるで「試練の連続」とも言える人生を歩んでいます。
これは、ギリシャ神話におけるヘラクレスが数々の困難に立ち向かいながらも、大きな存在へと成長していった物語と重なる部分が多くあります。
実際の出生データからタイソンのチャートを分析すると、小惑星ヘラクレスは彼の第9ハウス牡羊座に位置しているとのこと。
占星術的に見て「9ハウス=海外・高等な舞台」で「牡羊座=闘士」の力を発揮する配置であることから、若くして世界ヘビー級王者となり神話的ヒーローのような名声を博したことと符号します。
しかし同時に、この配置には「牡羊座=火星的エネルギー(怒り)の制御」が課題として表れており、実際タイソンは私生活での暴力事件やスキャンダルによってキャリアに傷が付く結果となりました。
ブログ筆者は「タイソンのヘラクレスは、その怒り(火星)の暴走が自らの栄光を損ねたことを示している」と分析し、まさにヘラクレス神話のように“人間的な弱点(激情)”が“神的な強さ”をも崩壊させうる教訓だと述べています。
この事例からわかるように、小惑星ヘラクレスは個人の生き様や人生の葛藤を深く照らす鍵となる存在です。
マイク・タイソンのような極端な人生を歩む人物のチャートにおいてこそ、その力強い象徴性が明確に現れます。占星術を実践する上で、このような著名人の事例を踏まえることは、象徴の意味を具体的に理解する大きな助けになるでしょう。
どう読むか?解釈の実際
実際の鑑定において、小惑星ヘラクレスの解釈事例はまだまだ少なく、一方で非常に個別性が高いものと考えています。
チャートの全体文脈を丁寧に読み解く必要があります。
ここでは、私ならどう読んでいくか?として、ヘラクレスがどのように働いていたのかを紹介し、その象徴の実践的な解釈に触れていきます。
例えば、ヘラクレスが第4ハウスに位置し、土星とトラインを形成する場合。
おそらく家庭環境が不安定であり、親からの圧力もあった幼少期。
その中で自立心を強く求められる状況もあり、特に家族との距離感に悩みつつも、最終的には自身の経験をバックグランドにして、家族問題を専門とするカウンセラーとして独立。
まさしく、対面の10ハウスに向けて社会に飛び出していく感じでしょうか。
ヘラクレスのストーリーから、「家庭を舞台とした試練を経て他者の癒し手となる」という鑑定ですね。
別の事例でも考えてみます。(私の事例です)
ヘラクレスが第8ハウスに位置し、月と緩めなコンジャンクションを形成。対面には土星がオポジションしています。
親との関係で心に深い傷を負った経験を持つ方は少なくありません。特に、幼い頃から親との間に激しい感情のぶつかり合いがあった場合、その記憶は長く心に残ります。
実際、私自身も親との関係の中で互いに感情をぶつけ合い、お互いを深く傷つけあった体験があります。(詳細は、鑑定などの時に・・またどこかで・・)
ここからも、感情という繊細かつ根深いテーマにおいて、試練と変容をもたらすことを意味しています。
第8ハウスは死と再生、また心の奥深くにある無意識の領域を象徴する場所です。そこにヘラクレスが位置することで、内面に潜む葛藤や感情との向き合い方が人生における大きなテーマとなるのです。
特に月との結びつきがある場合、そのドラマは家庭環境や母親との関係を通して現れやすくなります。抑えがたい怒りや悲しみをどう扱うか、自分の中でどう消化し、どのように変容させるかが課題となるのです。
このような配置を持つ人にとって、感情は時に暴力的な衝動にも、逆に深い癒しの源にもなり得る存在です。
今振り返れば、あのとき感じた激しい痛みは、単なる苦しみではありませんでした。むしろ、自分自身の感情と真剣に向き合い、それを理解し、超えていくための“通過儀礼”だったのではないかと感じています。
占星術的に見ても、ヘラクレスは試練と成長を結びつける象徴的な天体です。
そして、多く仮説や鑑定事例、自己鑑定で見ていく中で明らかになるのは、困難な状況こそがその人本来の資質を明らかにし、人生の重要な転機となるという事実です。
小惑星ヘラクレスは単なる困難の象徴ではなく、むしろそれを通して得られる力強い成長のプロセスを映し出す天体として捉えるべき存在です。
実際のリーディングにおいても、この天体の象徴性は単一的に扱うのではなく、チャート全体の文脈やその人の人生の流れと照らし合わせて丁寧に読み解くことが求められます。ヘラクレスの力は、痛みの中に隠された強さを引き出し、個人の内なる英雄性を呼び覚ます鍵となるのです。
小惑星ヘラクレスの占星術に関する総まとめ
最後に、本記事のまとめをしていきます。まだまだ鑑定事例の少ない小惑星ヘラクレス。ですが、その知名度や彼のストーリー、そして自己の鑑定からも、鑑定には外せないものと思い、取り入れています。
皆さんもぜひ、自身のホロスコープで解読にチャレンジしてみてください。ヘラクレスを扱うサービスはあまりありませんが、私の方でも鑑定サービスを用意しました。

- 小惑星ヘラクレスは1991年にキャロライン・シューメーカーによって発見された
- 小惑星番号5143に登録されており、比較的新しい分類に属する
- 地球軌道と交差するアポロ群に分類される近地球小惑星である
- 約2.48年(907日)の公転周期を持ち、動きが比較的速い
- 二重小惑星として伴星を持っていることが観測されている
- サイズは直径約4~5kmの岩石質とされる小型天体である
- 占星術的には「試練」「克服」「成長」を象徴する天体とされる
- ヘラクレス神話に由来し、12の試練の物語が解釈のベースとなる
- 現時点では公式なグリフ(記号)は存在しない
- 非公式に記号やアイコンが使用される事例が一部存在する
- ハウス配置によって試練が生じやすい人生領域が異なる
- アスペクトにより、挑戦の性質や乗り越え方が変化する
- 他の四大小惑星とは象徴や性質の方向性が大きく異なる
- ヘラクレスは男性的エネルギーや社会的達成を担う象徴でもある
- 鑑定事例からも困難と成長の関係性が読み取れる
全体の運勢を知ることも大切ですが、あなたが本当に知りたいのは“たったひとつの星”が映し出す物語かもしれません。
恋愛観、仕事での課題、あるいは小惑星が示す隠れたテーマ――。あなたの選んだ天体に光を当て、人生の核心を解き明かす鑑定をご用意しました。



理系出身・分析型の占星術師による【1つの天体を徹底的に深掘りする鑑定】はこちらからご覧いただけます。」👉 1つの星を主役にした深掘り鑑定はこちら